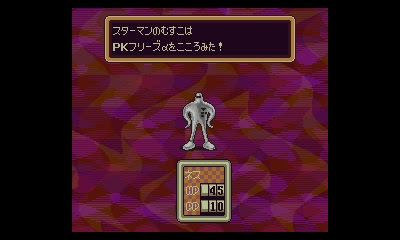どうも、ノンジャンル人生です。うおーーーーー!!!なんか色々タスクを終わらせた!!イエイ!
はい。以前New3DSのサイズ別メリット・デメリットを書いたので、今回は私個人のおすすめソフトを挙げようと思います。なんかすごくブロガーっぽい内容ですね・・・。アフェリエイトないんで何にも得るもんはないですけど。
1.とびだせどうぶつの森(コミュニケーション)

スローライフゲームであり、任天堂製の遊ぶ抗うつ剤(違う)。村長として村を任されたプレイヤーが、釣りや虫取り、どうぶつ達とのふれあいなど、小さな村の中で気ままに暮らすゲーム。家を立てた借金の支払いはあるものの、基本的にゴールは設定されておらず、自分の好きなことに集中することが出来る。今作では公共事業として村にいろんなものを建てることが出来る。
とにかく居心地良い空間が魅力。住人の引っ越し関連で問題点は多かったものの、最近のアップデートで緩和。しばらくこれが億劫で触れなかったので、本当に良かった・・・。
2.モンスターハンタークロス(ACT)
人気アクションシリーズであり、自分の初モンハン。旧作モンスターやフィールドが集合したお祭り作品とあって、コンテンツ量が異様なほどある。
モンハンの魅力は散々語られてきたけど、やはりデカいモンスターと死闘を繰り広げられるのは、それだけで楽しい。難易度高めなアクションではあるけど、反射神経より立ち回りが重要なゲームで、苦手な人でも共闘や装備を駆使すればなんとかなる。シリーズ歴代の有名なモンスターやフィールドが多々用意されているので、入門編として最適な一作。
デメリットはやはり3DSと激しいアクションとの相性の悪さ。あと、どうしてもフィールドが手狭に感じてしまう。環境があるならSwitch版ダブルクロスを買うか、PS4のモンハンワールドを待つのも手。
3.星のカービィトリプルデラックス/ロボボプラネット(ACT)

Wii版の流れを汲む、星のカービィの3DS作。マルチプレイは採用してないものの、ひとりプレイのアクションとしては両方ともボリュームが多め。ステージクリア型の横スクロールアクションとしては敷居は低いが、各コピー能力ごとのアクションのバリエーションが多く、適当に遊んでも満足感が高いのが強み。立体視もよく完成されている。
だが、こんな真面目に語る必要はまったくなし。ゆるく可愛らしいアクションに魅力を感じたなら、アクションが得意だろうが苦手だろうが間違いなく買い。SFC時代と比べても、キャラの仕草やフィールドギミックなど、可愛らしい世界観を徹底的に作り上げている。かわいいは正義なのだ。
TDXはいつものカービィ、ロボボはちょっと変化球の世界観で、とりあえずやってみたいならTDXからがおすすめ。
4.新・光神話 パルテナの鏡(ACT/STG)
カービィ・スマブラの生みの親桜井氏が手がけた、ネットで3DSの名作を挙げた場合に必ず名前が出るソフト。タッチペン操作で天使ピットを操り、復活したメデューサと戦いを繰り広げる。ステージ前半は空中STG、後半は地上ACTという構成になっており、ステージボリュームも驚くほど多い(アニメで言うところの2クール分ある)。操作難易度は高いもののボタンをカスタマイズでき、上手くコントロールできた時の気持ち良さも秀逸。物語は壮大であるものの、ノリのほとんどがコメディ寄り。
パッケージに付属のスタンドがない場合は片手持ちをしなければならず、LLとの相性はあまり良くないので注意。左利きはやや不利(左対応はしているが、ペン右手持ちの方がやりやすかった)
5.ゼルダの伝説 神々のトライフォース2(ACT)
SFCの見下ろし型アクションの金字塔が、まさかの20年越しの続編。ストーリーは直接繋がっていないものの、前作のマップが採用されており、遊びやすさと懐かしさを兼ね備えた一作(ちなみに自分は前作を今プレイ中)。ゼルダの難点でもある、ダンジョンの決まった攻略順が解消されており、壁画ギミックと合わせて、探索がより自由で楽しくなったのが印象的。立体視も良好。ブレスオブザワイルドのような広大さはないものの、箱庭をちまちま攻略する体験はまた別の魅力がある。
もちろん時のオカリナ3Dやムジュラの仮面3Dも名作なので、こちらもぜひ。
6.STEELDIVER SUBWARS(STG)
フリートゥプレイであるものの、千円払って40時間遊び倒したゲーム。潜水艦を操作して敵艦を撃破する、チーム対戦型のシューティング。TPSに近いが、水中ゆえにゆっくりと照準を合わせるのが特徴的。相手の動きを読み、撃破したときの喜びもひとしお。シングルプレイも楽しい。
7.サバクのネズミ団!(SLG)

正直3DSだけで配信しているのが勿体無いほどの隠れた名作(でも3DSの画面はちゃんと駆使している)。砂漠の上を走る船を運用&改造して、ネズミたちが伝説の黄金郷を目指すSLG。拠点間を移動しながらスクラップを集め、船の設備や食料をクラフトしていく。砂漠には危険がいっぱいで、武器を設置して強敵と戦う必要もある。ネズミたちに役割を与えて放置するタイプのゲームだけど、結構忙しい。忙しいけど、ネズミたちがいちいちかわいくて見とれてしまう。
作業ゲーがしたい人なら満足できる一作。曲もオールドミュージック調で魅力的なので、癒やしを求めたい人にもオススメ。
8.3D アウトラン(ドライブ)
セガの名作アーケードゲームの移植であり、立体視を使ったソフトの中で最も使い方が上手く感じたのがこのソフト。分岐点で走行ルートを自由に選択しながら、時間内にゴールを目指すドライブシュミレーション。奥から高速で流れてくる立体背景が、スピード感があってとても気持ち良い。遺跡、海岸線、花畑と、運転中のロケーションも抜群。曲も爽快でステキ。
タイムトライアルは出来るけど、CP対戦モードもなく、あくまでレースではなくドライブゲームなので注意。
9.ゼノブレイド(RPG)

Wiiから携帯機に移植された、巨神と機神の上を駆け抜ける大作RPG。ユニークな世界観はもとより、その再現されたフィールドの完成度は国産RPGでも随一。
プレイするなら立体視があり画面サイズ大きめの、New3DSのLLが断然オススメ。もちろんWii版WiiU版でもOK。Swich版はもう少し先だろうか?
詳しく書いたブログ記事はこちら。
『Xenoblade ゼノブレイド』、未来を変える冒険を終えて
10.アライアンス・アライブ(RPG)

自分がイチオシする群像劇RPG。ゼノブレイドに比べるとビジュアルや壮大さは劣るが、SFC~PS期のようなコンパクトかつテンポの良い展開のおかげで、夢中になって一気に遊んだRPG。戦術性の高い戦闘やギルドメンバー集めなど遊びごたえもある。3DSで自分が一番面白かったゲーム。
詳しく書いたブログ記事はこちら。限界突破の6,000文字。
アライアンス・アライブ:RPGへの愛が注ぎ込まれた、失われた青い空を取り戻す物語
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
以上。いやぁー、最初はなんやかんや言われた3DSも、6年も立つと良作揃いますね。立体視も役目を終え、ポケモンやFEがSwitchに移行宣言して、本格的に3DS世代も終わるとなると感慨深いものがあります。とは言え、VCや旧作遊び倒すならまだまだ現役で遊べそうなので、New2DS買おうか悩みどころ(New3DSが画面が小さすぎて目が疲れてきた。歳か…)。もちろんSwitchに行くのもありなんですけど、なかなか足を踏み入れられないのじゃ。
それでは~。